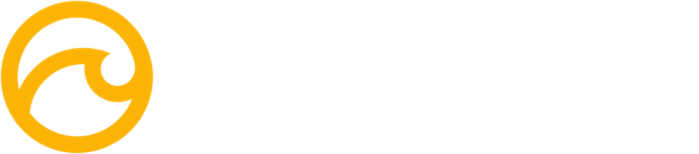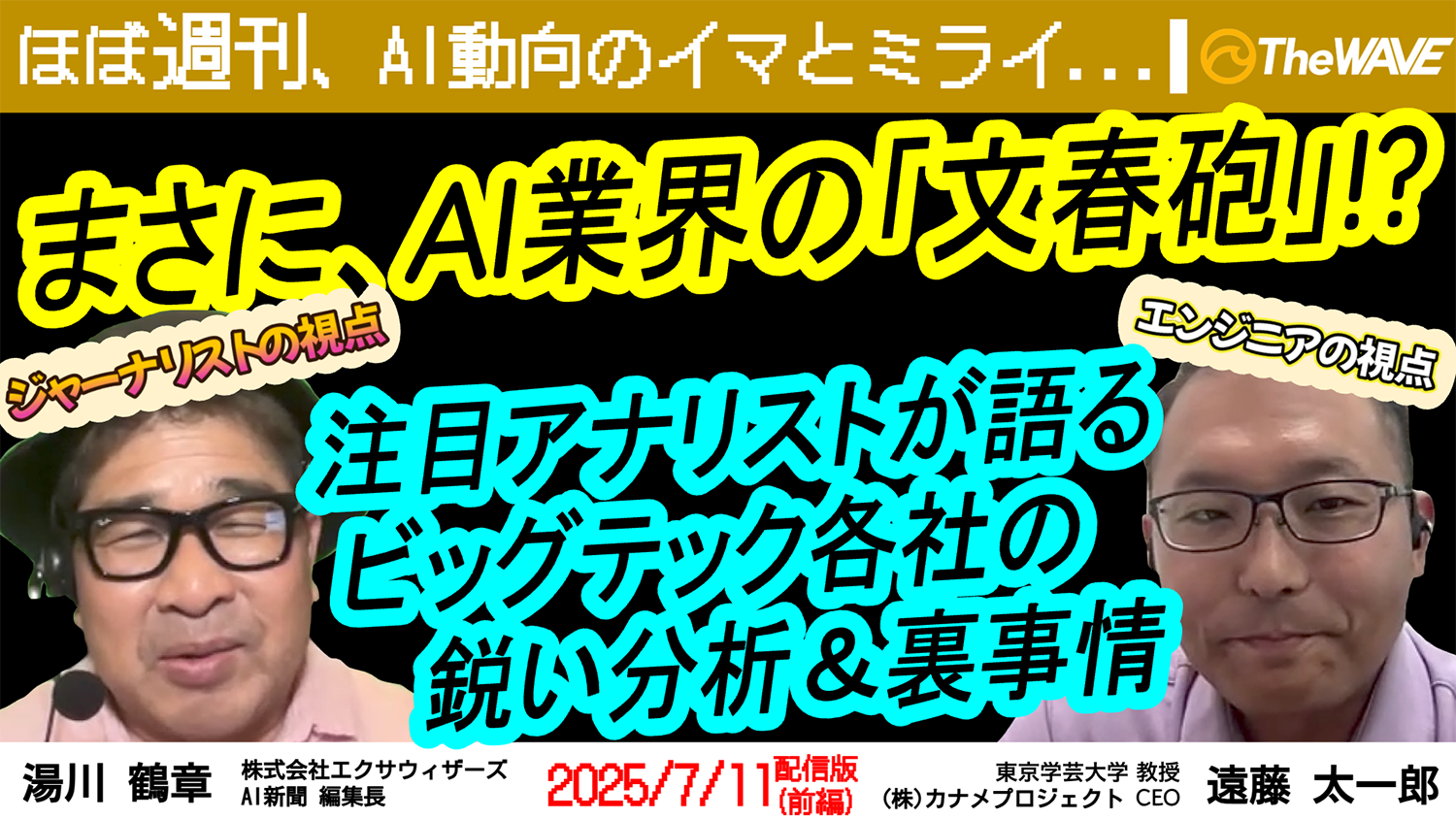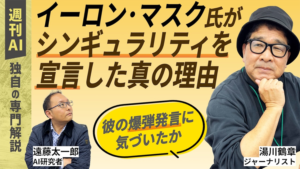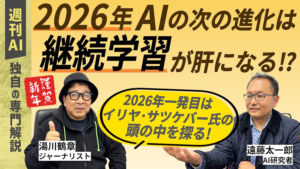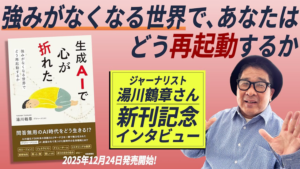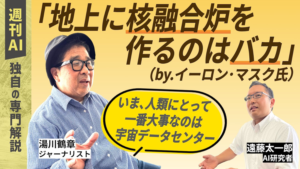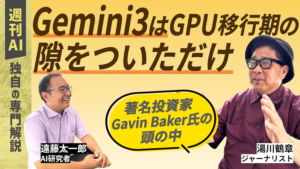本編動画
2025年7月11日に、以下の目次で「ほぼ週刊、AI動向のイマとミライ」動画を配信しました。
0:59 (1)今週は、注目のアナリスト・Dylan Patel氏の貴重インタビューより
3:28 (2)Dylan Patel(ディラン・パテル)氏って、何者?
6:51 (3)MetaのAIモデルの組織問題
11:14 (4)Scale AIの買収とMetaの戦略転換
14:31 (5)MicrosoftとOpenAIの関係
17:11 (6)GPT-5になるはずだったOrionはなぜ失敗したのか
20:41 (7)Appleの課題
23:46 (8)AMD vs Nvidia
28:08 (9)xAIとGrokについて
30:02 (10)超知能(ASI)について
各チャプターの概要は以下の通りです。
(1)今週は、注目のアナリスト
・Dylan Patel氏の貴重インタビューより
https://www.youtube.com/watch?v=cHgCbDWejIs&t=1s
(2)Dylan Patel(ディラン・パテル)氏って、何者?
・AI/半導体分野の調査会社 SemiAnalysis の創業者・CEO 兼チーフアナリスト。メンバー32人。Substack の購読者は5万人超(テック系で世界2位)。NVIDIA、TSMC など主要企業の設備投資や歩留まり、クラウド各社のGPU配置台数のリーク分析で注目を集める
・Oracle の計算資源拡大策を詳細に解析。大企業向けGPU市場での台風の目と宣言
・AI電力需要と送電網リスク トレーニング負荷が停電を引き起こすと警鐘。
・米・UAE・KSAのAI協定を取り上げ、地政学リスク×インフラ投資の視点を拡散。
(3)MetaのAIモデルの組織問題
・MetaのLlama 4は「悪くはないが、世界を変えるほどではなかった。Behemothモデルは、トレーニング方法や設計上の問題からリリースが遅延し、もしかしたらリリースされないかもしれない。1つのモデルは、DeepSeekに対抗するためのやっつけ仕事。客観的に見てひどい出来
・一方で、OpenAIは、Sam AltmanではなくGreg Brockmanが非常に優秀な技術リーダー。Mark Chenも素晴らしい技術リーダー
・研究の進むべき方向性を選ぶ「センス(taste)」と直感が重要。それが今のMetaには不足している
(4)Scale AIの買収とMetaの戦略転換
・Metaによる買収後、既存顧客だったGoogleはScale AIに今年2億5000万ドル支払う契約だったが、それを中止。OpenAIはScale AIとのslackのコネクションを切った。会社としてはScale AIは大打撃
・数ヶ月前までマーク・ザッカーバーグ氏はAGI(汎用人工知能)に興味がなかったのに、急にスーパーインテリジェンスが重要だと言い始めた。遅れを取ったので、どうすれば追いつくかと焦った結果、Alexandr Wang氏(Scale AI CEO)への声がけにつながった
・Patel氏はIlya Sutskever氏を評価。Sutskever氏がASIと言い始めてから、皆がそれに追随し始めた
(5)MicrosoftとOpenAIの関係
・OpenAIはMicrosoftの助けなしには、ここまで来れなかった。MicrosoftはOpenAIもコントロールしたかったけど、独禁法の関係でそれは難しい。なのでレベニューシェアや、利益保証、AGI完成までの知的所有権であるとか非常にややこしい契約になっている
・AGIが完成したかどうかはOpenAIが決められる。でももし今AGI完成を宣言したら、Microsoftの法務部門が全力でOpenAIを訴えるのは間違いない。
・でもAGIなのかASIなのかはいずれ完成する。完成して検証している間にMicrosoftにはコードや重みを全てコピーできる権利がある。完成したAIはOpenAI一社のものではなく、Microsoftも同じものを所有できることになる。これはOpenAIの投資家にとって不安材料。
・一方でMicrosoftは独禁法調査を非常に怖がっている。OpenAIはMicrosoft以外のクラウドの使用を禁止する契約になっていたけど、昨年、その条項は削除された。
(6)GPT-5になるはずだったOrionはなぜ失敗したのか
・開発コード名Orionは、GPT-5としてリリースする予定だったが、いろいろ問題が重なりGPT-4.5としてリリース。それでも利用されずに廃止。結局それほど役に立たず、遅すぎ、費用がかかりすぎた
・Orionに手間取っている間に、リーズニングモデルのチームがo1の開発に成功した。リーズニングモデルで良質の合成データを作れるようになった
(7)Appleの課題
・Appleは非常に「保守的な企業」。AI研究者は研究を公開したがる傾向があるのに対し、Appleは秘密主義の企業。Appleには研究者を惹きつける魅力がない
・AppleはNVIDIAと仲が悪い。特許訴訟や不具合問題で揉めた歴史があり、Appleは半導体やデータセンターを独自開発してきた
・オンデバイスAIには否定的。オンデバイスAIのセキュリティは利点だが、ユーザーはセキュリティよりも無料が好き。ユーザーがセキュリティを理由に高価なハードウェアを選ぶことは少ない
・さらに、AIの最も価値のあるユースケースのほとんどは、既にクラウドにあるデータにアクセスする必要があるため、オンデバイス処理の必要性が低い
(8)AMD vs Nvidia
・AMDはNvidiaに追いつこうと努力しており、一部のハードウェアは優れているが、BlackwellのようなNvidiaの最新チップセットには劣っている
・Nvidiaは、儲かりすぎている大手クラウドプロバイダーの利益率を下げるために、CoreWeaveやOracleなどの50以上の小規模なクラウド企業を優先し、GPUを供給。しかし、NvidiaがLeptonという企業を買収し、「DGX Lepton」という自社競合のクラウドサービスを開始したことで、これらのクラウド企業を怒らせている
(9)xAIとGrokについて
・Grok 3は期待以上に良いモデル。特に「ディープリサーチ」がOpenAIより速い。人種問題などセンシティブなトピックでも遠慮なくデータを提供する
・イーロン・マスクがGrok4がこれまでにないようなモデルだと言っているが、リリースされるまで分からない。各社とも「他社とは大きく異なる方法で開発している」と言うが、私から見れば皆同じような方法でモデルを開発しているように見える
(10)超知能(ASI)について
・オープンソース企業も自分たちが最先端になればクローズドソースになる。最先端は常にクローズドソース
・超知能に最初に到達するのはOpenAIになる。これまでの主要なブレークスルーを起こしてきたから。次にAnthropic。3位は、Google、x.AI、Metaのどこがきてもおかしくない状態
個別テーマ解説動画
また、各テーマに分割した動画も配信しました。興味のあるトピックに応じてご覧ください。
[切抜解説]MetaのLlama 4は「悪くはないが、世界を変えるほどではなかった」by.Dylan Patel氏
0:00 研究の進むべき方向性を選ぶ「センス(taste)」と直感が、今のMetaには不足している
4:16 急に超知能が重要だと言い始めたザッカーバーグ氏(Meta CEO)の真意
※サムネイル画像はManfred RichterによるPixabay画像を活用
登壇者情報

遠藤 太一郎
株式会社カナメプロジェクト CEO
国立大学法人東京学芸大学 教育AI研究プログラム 教授
AI歴25年。18歳からAIプログラミングを始め、米国ミネソタ大学大学院在学中に起業し、AIを用いたサービス提供を開始。AIに関する実装、論文調査、システム設計、ビジネスコンサル、教育等幅広く手がけた後、AIスタートアップのエクサウィザーズに参画し、技術専門役員としてAI部門を統括。上場後、独立し、現在は株式会社カナメプロジェクトCEOとして様々なAI/DAO/データ活用/DX関連のプロジェクトを支援する。国際コーチング連盟ACC/DAO総研 Founder等

湯川 鶴章
株式会社エクサウィザーズ AI新聞 編集長
米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。