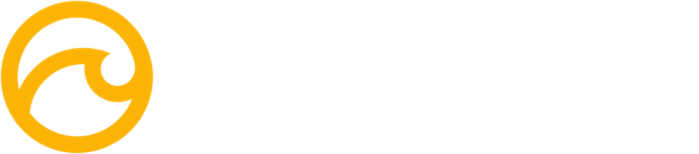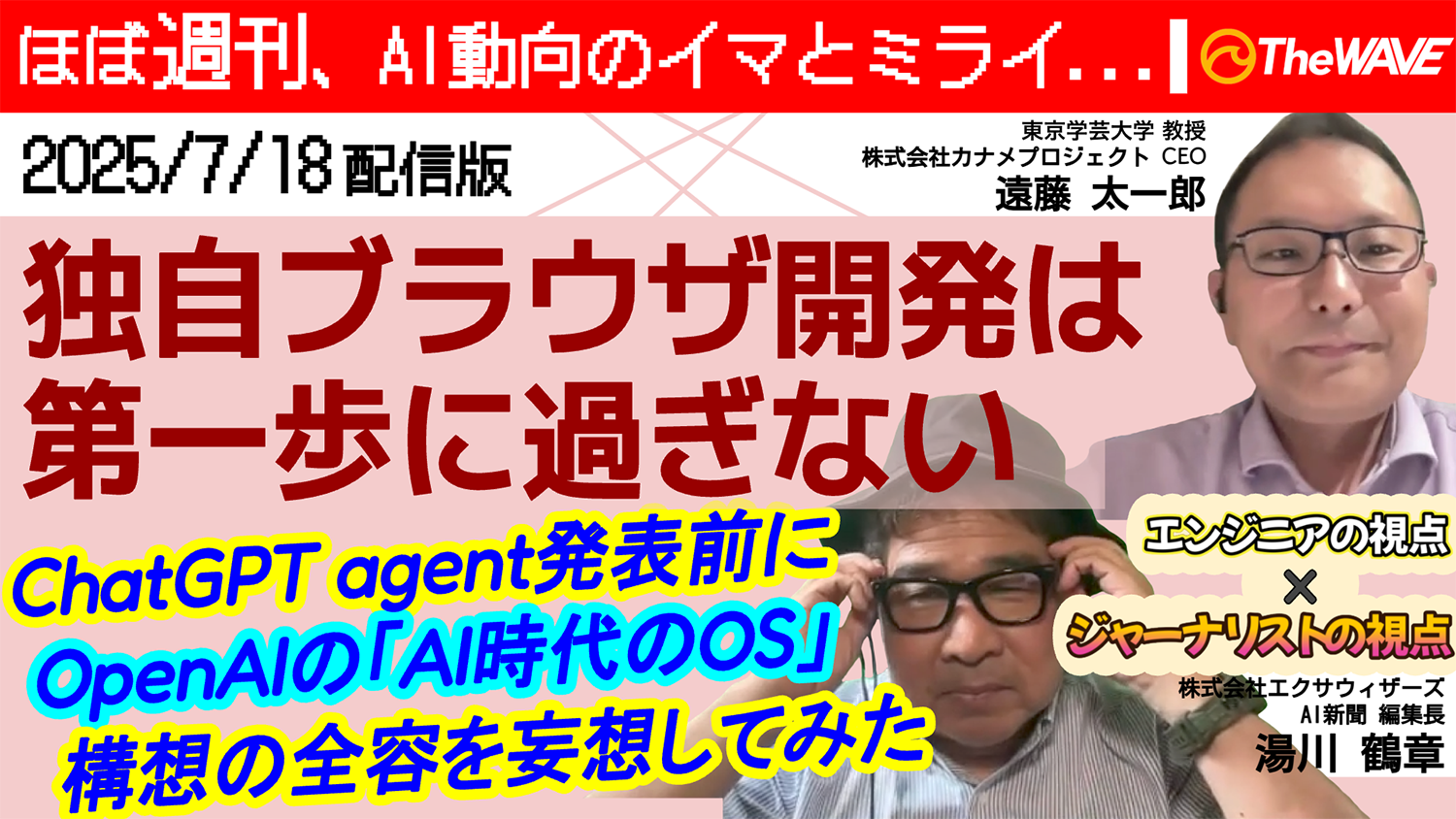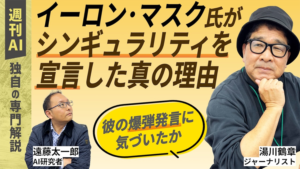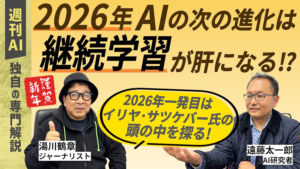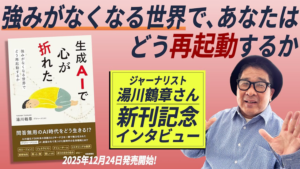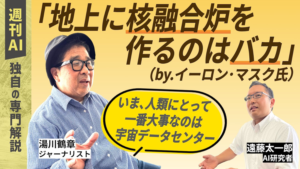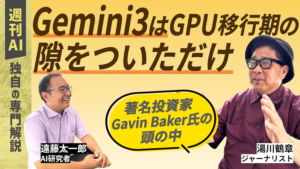本編動画
2025年7月18日に、以下の目次で「ほぼ週刊、AI動向のイマとミライ」動画を配信しました。
1:02 (1)今週は、前週の緊急収録「独自ブラウザ開発がAI覇権への第一歩」の続き
3:38 (2)前回の緊急収録に対していただいたコメントご紹介
6:59 (3)Perplexityのブラウザ「comet」
23:07 (4)AI時代のOSになる
34:34 (5)Sam Altman氏はもっと大きなことを考えていそう
50:36 (6)ブラウザ開発はバカげた判断!?あなたはどう思う?
各チャプターの概要は以下の通りです。
(1)今週は、前週の緊急収録「独自ブラウザ開発がAI覇権への第一歩」の続き
https://youtu.be/GxxtjtAALhk
(2)前回の緊急収録に対していただいたコメントご紹介 コメントお寄せいただいた皆さま、ありがとうございました!
(3)Perplexityのブラウザ「comet」
・利用ケース紹介:ベストなハイブリッド自転車のリサーチ、音声で動画の中から最適な箇所を抽出、要約、ECサイトでの検索・購入、旅行プラン策定、レシピ作成、Redditの長いやり取りの要約・動画探索など
・Aravind Srinivas氏(Perplexity CEO)へのインタビュー動画より
https://youtu.be/2jOnoTEk-xA?si=rw9MpFiFYVinOIow&t=1128
・「Perplexityは、ブラウザを「認知的なオペレーティングシステム」のように機能させることを目指している」
・Perplexityのブラウザは、検索、情報収集、エージェント的なタスクを一つのオムニボックスで実行できるように設計。AIアシスタントがブラウザに深く統合され、新しいタブページやウェブページのサイドバーでユーザーをサポートする
・個人のメール、カレンダー、ショッピングアカウントなどと連携し、ユーザーの代わりにリサーチやタスクを並行して非同期に実行できるようになる
・チャットボットでは不可能な、複数のタブへのアクセス、閲覧履歴の活用、フォームへの入力、支払い、商品の購入、定期的なリサーチといった複雑な多段階タスクの実行が可能になる
・「MCPは素晴らしいけど、誰もがMCPに準拠するわけではない。MCPに準拠しないサービスでもウェブサイト上で展開しているのなら、ブラウザを操作することでどんな情報にでもアクセスできる。なので独自ブラウザを持つことが重要」「ここまでサブスクモデルが有効だとは思わなかった。想像していた以上に大きな収益になってきている。サブスクの代わりに従量課金というモデルも出てくるのかもしれない。いずれにせよ人を雇うより安いという理由で、ユーザーはAIエージェントに十分な料金を支払うように思う」
(4)AI時代のOSになる
・3段階で「OS化」が広がるイメージ:ブラウザ統合(今)→ローカル統合(1〜2年)→ネイティブ OS & ハード(2〜3年)
・3段階目の「ネイティブ OS & ハード」では、AI専用 SoC+センサーを備えた “新しいタイプのコンピュータ” が登場する!? ローカル推論で常時動き、オフラインでも個人データを扱う想定
・Sam Altman氏が学生たちを例に「ChatGPT を operating system のように使う」と語ったのは、この B→C の移行期 を指している
https://www.businessinsider.com/sam-altman-people-use-chatgpt-differently-depending-age-2025-5?utm_source=chatgpt.com
・どうやってローカル/社内データにつなぐのか?:公式コネクター、ファイル統合システム、企業データ
・企業データにまつわる「AIぐるぐるモデル」はどうなるのか
・ユースケース別に見る「OS化」シナリオ:PC ファイル整理、会議準備、社内レポート等
・サイト側・プラットフォーム側の動き:コントロールプレーンを OpenAI が獲るのか、OSベンダーが巻き返すのかが次の主戦場
・AI時代のOSにまつわる課題とリスク:プライバシー境界、権限管理、レギュレーション
・Altman のいう「ChatGPT-OS」は、「公開 Web → ローカル PC → 企業データ → AI ネイティブ端末」へ、自然言語インターフェースと Operator エージェントを “同じチャット画面” のまま広げていく構想
・ブラウザ統合はその第一歩に過ぎず、ファイル操作・社内基幹システム・専用ハード まで一気通貫で扱えることこそが「OS 化」の本命だと見ておくと、将来像を描きやすいだろう
(5)Sam Altman氏はもっと大きなことを考えていそう
・セコイアキャピタルのYouTubeチャンネルより「OpenAI’s Sam Altman on Building the ‘Core AI Subscription’ for Your Life」
https://youtu.be/ctcMA6chfDY?si=6Cs8T7MjM1LaOsf3
・以下の動画ですでに紹介したもの(2025/05/19配信動画)
https://www.youtube.com/watch?v=ZDuqwGJFMtY
・Altman氏が語った断片的なビジョン:核になるのは“コア AI サブスクリプション”、体験面では“AI 時代の OS”、裏側では“HTTP レベルの新プロトコル”、開発者向けには“API / SDK”
・OpenAIブラウザ × OS 戦略:①コアAIサブスクリプション、② AI-OS体験、③フェデレーテッドWebプロトコル
・AI時代の新プロトコル案:AI-Auth、AI-Meter、AI-Scope、Context-Passなど。このプロトコルが普及すれば、サイトは「UI+広告」で稼ぐ必要がなくなり、データAPI+AI利用料へモデル転換できる!?
・開発者エコシステム:SDKが握るレベニュープール
・OpenAI が押さえているのは「モデル性能 × ID/メモリ × プロトコル」の先行規格。逆に言えば Google/Apple が自社 OS に「パーソナル AI を標準実装」し、プロトコル主導権を奪えば勢力図は揺らぐ
・今後12か月の注目チェックリスト:Operator Browserβの UX と拡張互換、MCP / HTTP-AI の公式ドキュメント公開、「Sign-in with OpenAI」ローンチ時期、Publisher API における中小媒体の料率、Apple・Google の AI-OS 動向(WWDC / I/O)
・Altman が描くのは 「AI=OS」「プロトコル=鉄道網」「サブスクリプション=電力」 という総合インフラモデル。ブラウザはその先頭車両にすぎず、真に競争が起こるのはID/メモリ基盤を誰が握るかと、課金レイヤーを誰が標準にするか。ユーザーが月額で“自分専用 AI”を持ち歩き、開発者は SDK でそこへ機能を接続し、サイトはデータと料金テーブルで稼ぐ。OpenAI はその未来図を最速で実装に移しつつある
(6)ブラウザ開発はバカげた判断!?あなたはどう思う?
Grok 4 Wows, The Bitter Lesson, Elon’s Third Party, AI Browsers, SCOTUS backs POTUS on RIFs
https://youtu.be/KypnjJSKi4o?si=zCrLtSffNAvS3Bbt&t=3134
・「今日ブラウザを開発するのは非常にバカげた資本の使い方だ」(Chamath Palihapitiya氏)
・理由①:シェア獲得のハードルが異常に高い
https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide?utm_source=chatgpt.com
・理由②:維持コストが重い
https://oviyabalan.medium.com/tldr-arc-browsers-future-3d392cc91172?utm_source=chatgpt.com
・理由③:収益ストリームが細い
https://sacra.com/c/brave/?utm_source=chatgpt.com https://brave.com/blog/2025-search-ads-update/?utm_source=chatgpt.com
・理由④:機会費用が巨大
https://techcrunch.com/2025/07/09/perplexity-launches-comet-an-ai-powered-web-browser/?utm_source=chatgpt.com
・理由⑤:UI自体が溶解しつつある
https://www.theverge.com/2024/11/27/24302415/doj-google-search-antitrust-remedies-chrome-android?utm_source=chatgpt.com
個別テーマ解説動画
また、各テーマに分割した動画も配信しました。興味のあるトピックに応じてご覧ください。
[切抜解説]Perplexityのブラウザ「Comet」ってどうなの?
0:00 様々な利用ケース紹介
8:52 「認知的なオペレーティングシステム」のように機能を目指している
※サムネイル画像はJanによるPixabay画像を活用
登壇者情報

遠藤 太一郎
株式会社カナメプロジェクト CEO
国立大学法人東京学芸大学 教育AI研究プログラム 教授
AI歴25年。18歳からAIプログラミングを始め、米国ミネソタ大学大学院在学中に起業し、AIを用いたサービス提供を開始。AIに関する実装、論文調査、システム設計、ビジネスコンサル、教育等幅広く手がけた後、AIスタートアップのエクサウィザーズに参画し、技術専門役員としてAI部門を統括。上場後、独立し、現在は株式会社カナメプロジェクトCEOとして様々なAI/DAO/データ活用/DX関連のプロジェクトを支援する。国際コーチング連盟ACC/DAO総研 Founder等

湯川 鶴章
株式会社エクサウィザーズ AI新聞 編集長
米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。