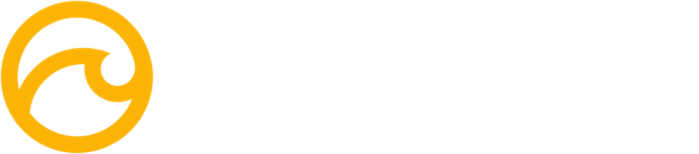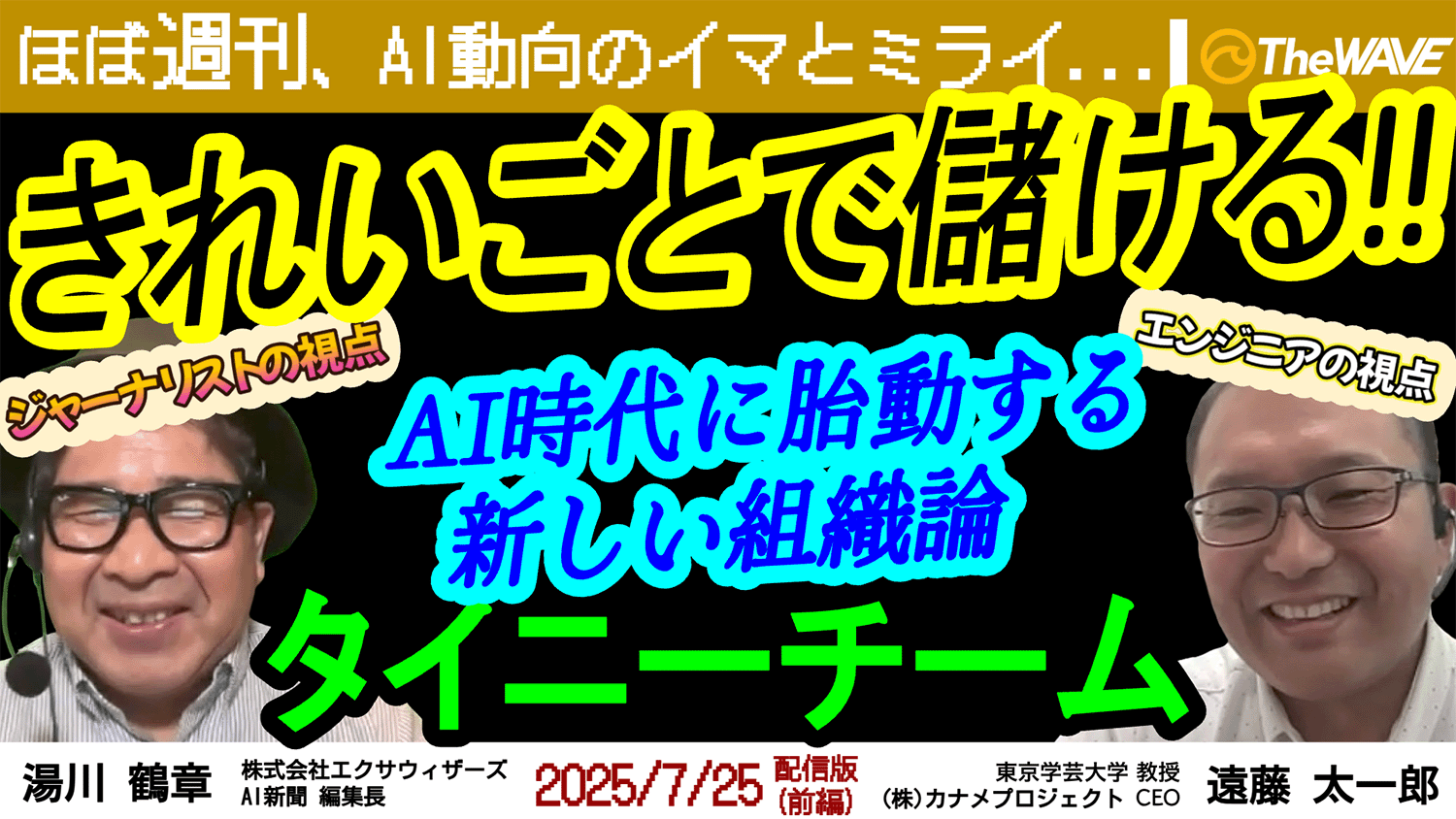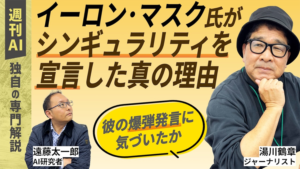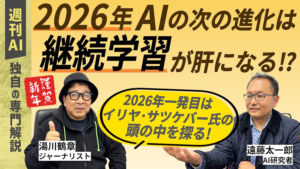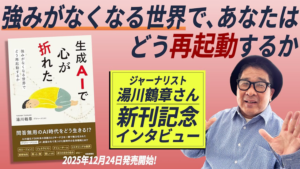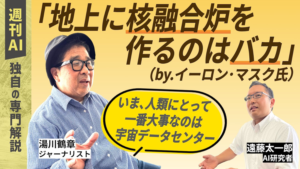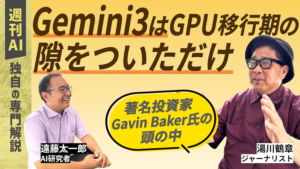本編動画
2025年7月25日に、以下の目次で「ほぼ週刊、AI動向のイマとミライ」動画を配信しました。
1:01 (1)少人数で大きく稼ぐ「タイニー(小さい)チーム」なAIスタートアップが急増中
3:14 (2)タイニーチームが急増しているの理由
6:55 (3)プレゼンツール「Gamma」の場合
15:43 (4)ブラウザ内AI開発エージェント「Bolt」の場合
20:36 (5)教育アプリ開発などの「Oleve社」の場合
28:47 (6)ワークフロー自動化ツール「Gumloop」の場合
34:09 (7)社会課題 × タイニーチームの成功例(2024-25)
36:11 (8)タイニーチームの特徴7選
40:27 (9)ようやく「きれいごとで儲ける」ことができる時代になってきた
各チャプターの概要は以下の通りです。
(1)少人数で大きく稼ぐ「タイニー(小さい)チーム」なAIスタートアップが急増中
(2)タイニーチームが急増しているの理由
・月額3,000〜30,000円のAIサブスクが常識化、GPU推論コストを理解するユーザーにとっては有料でも「仕方がない」、少人数でAIツールを使い倒して効率運営する一方で利用料金が高単価なので10人程度のAIスタートアップが急成長している+小さい会社の方が楽しい
・このトレンドに最初に注目したのは、AI開発者コミュニティ「Latent Space」
https://www.latent.space/p/tiny
・タイニーチーム(Tiny Team)の定義:目標は「ARR(年間経常利益) ÷ FTE(フルタイム換算従業員数)>100万ドル」。一人当たり、約1億5000万円以上儲けているかどうか。稼げている企業が、AI時代のtiny team組織 ・シンプル・高速・自動化が共通項
(3)プレゼンツール「Gamma」の場合
https://youtu.be/q8zoXAbmJdI?si=hOViVZ8nfvJlNmpX&t=545
https://youtu.be/q8zoXAbmJdI?si=Yn8GZujq6zjM-vBR
・従業員数30人で、5000万ユーザー。この規模のビジネスなら、2、3年前の企業なら従業員数は今の10倍ぐらいが必要だろう。30名/5,000万ユーザー/ARR $50 M
・取り組み①:ジェネラリスト採用。多様なスキルを持ち、異なる専門分野の知識を結びつけられる人材。ジェネラリストは、学習意欲が高く、教えることも得意。面接の際に、新しいスキルを他者に教える能力があるかどうかを重視する
・取り組み②:プレイヤーコーチ体制。AIが非常に速く進化する環境において、トップダウンの指示だけでなく、現場で適応し、優先順位を再設定できるプレイヤーコーチが重要
・取り組み③:同じ価値観のチーム。小規模なチームでは、ブランドと文化への投資が非常に重要。ブランドは文化の反映であり、文化は企業の価値観そのもの。新しいチームメンバーは、会社の価値観を共有し、同じように行動することが求められる。これは、小規模なチームでは「悪い採用」が全体に与える影響が大きいため。チームの核となる価値観と行動を明文化し、新入社員のオンボーディングにも活用。 ◦ これにより、「小さな部族」のような感覚が生まれ、継続性、透明性、そして共有されたコンテキストが醸成され、高い生産性につながる
・組織が小さいほどプロダクト構造もシンプルになり、ユーザー価値に直結する機能へリソースを集中できる
(4)ブラウザ内AI開発エージェント「Bolt」の場合
https://youtu.be/s8RM8uYxkoY?si=Q6Uk9vAgABM727T7
・ローンチ:2024年10月3日。わずか15名 のチームで開発。リリース60日でARR2,000万ドル(約30億円)、2025年3月には4,000万ドル(約60億円)を突破。ユーザー数は500万超
https://www.businessinsider.com/stackblitz-bolt-silicon-valley-hottest-ai-coding-startup-nearly-died-2025-5
・基本哲学:Fewer people, more context per head (人数が少ない方が、一人当たりの守備範囲は広くなる)
・ベンチャー企業が、ヒットを打つためには、できるだけいろんな挑戦が必要。そのためには、低い資金燃焼率と少ない人数が不可欠
・サポート業務にはAIツールが大きく貢献。特に「Parah Help」のAIアシスタント「SAM」は、チケットの90%を自動で処理し、50人分の採用を不要にした。
(5)教育アプリ開発などの「Oleve社」の場合
https://youtu.be/pQz-PgA1eJw?si=v-v2eq6tsibbZBGa&t=722
・4〜5名/9か月でARR $6 M/500万ユーザー。最終目標は1人10億ドル。2023年1月26日、TikTokにQuizard AIモバイルアプリの動画をアップしたところ何百万回の見られ、30時間で1万ユーザーを獲得
・運営方針①:ゼネラリストを雇用。雇うか、全く雇わないか 2、3の補完的な専門分野のスキルを持つ人材を厳選して採用
・運営方針②:スーパーツール。LaunchDarklyと言う機能管理プラットフォーム。ソフトウェアチームが新しい機能を素早く安全にリリースできるツール。それをmanual traffic load balancer として活用している
・組織形態:ハーベスターとカルティベーター
・社内の全員が「各自のチーフオブスタッフ(秘書部長みたいなエージェント)」を持つ
・自動化の3段階:段階1(人間主導のツール)、段階2(ワークフロー自動化)、段階3(自律的な意思決定システム)
・究極のビジョン:最終的に「1人 billion dollar companies(1人で10億ドル企業)」のポートフォリオを構築することを目指す
(6)ワークフロー自動化ツール「Gumloop」の場合
https://youtu.be/Qw9P1zvCupE?si=I–4-IPvfwhhNKyP&t=38
・目標は少人数で大きく儲ける。非常に慎重候補者を選ぶ。「心から興奮しないなら、採用しない」
・取り組み:合宿。AirB&Bで一軒家を借りて4日間、寝食を共にして働く。4日間で3週間分の仕事が可能。頻繁にこうした合宿を行い、候補者もこの合宿に参加してもらうことで一緒に働きたいかどうかを決めた
・運営方針①:会議をしない。優秀な人を雇っているので、彼らの自主性に任せている。社長はクライアントの話の中で気づいたアイデアを開発者に伝えるだけ
・運営方針②:社内業務を可能な限り全て自動化。自社製品であるGumloopを駆使し、自動化できないものがあれば、それを自動化するための機能をGumloop上に構築する。ユーザーから1日平均5万通のメッセージが寄せられるが、AIにそれを読ませて、どのような機能を開発すべきかを提案させている
(7)社会課題 × タイニーチームの成功例(2024-25)
・Rainforest Connection(違法伐採・生物多様性喪失→ 再利用スマホ+AI音響モデルでチェーンソー音を即検知)
・Karya(データ労働の搾取構造 & 低所得農村の雇用不足→ “世界初の倫理的データ協同組合”で音声・テキスト収集、労働者にロイヤルティ還元)
・Chatloop(難民の語学学習 & 孤立→ ボランティアと難民をマッチするメッセージングAI(5分/日の対話を設計))
・Sully.ai(医療人材不足・待ち時間⻑期化→ “AI従業員”を月$1,200/席で病院へ貸与(受付・通訳・看護補助Bot))
(8)タイニーチームの特徴7選
・若い
・雇用のこだわり
・会議がない
・AIツールを多用(Cursor、LaunchDarkly、Parahelp、Railway、Gumloop、Lindyなど)
・仲良しチームで儲ける
・きれいごとで儲ける
(9)ようやく「きれいごとで儲ける」ことができる時代になってきた
登壇者情報

遠藤 太一郎
株式会社カナメプロジェクト CEO
国立大学法人東京学芸大学 教育AI研究プログラム 教授
AI歴25年。18歳からAIプログラミングを始め、米国ミネソタ大学大学院在学中に起業し、AIを用いたサービス提供を開始。AIに関する実装、論文調査、システム設計、ビジネスコンサル、教育等幅広く手がけた後、AIスタートアップのエクサウィザーズに参画し、技術専門役員としてAI部門を統括。上場後、独立し、現在は株式会社カナメプロジェクトCEOとして様々なAI/DAO/データ活用/DX関連のプロジェクトを支援する。国際コーチング連盟ACC/DAO総研 Founder等

湯川 鶴章
株式会社エクサウィザーズ AI新聞 編集長
米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。