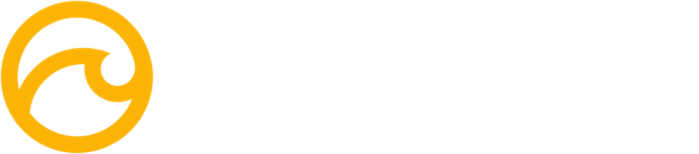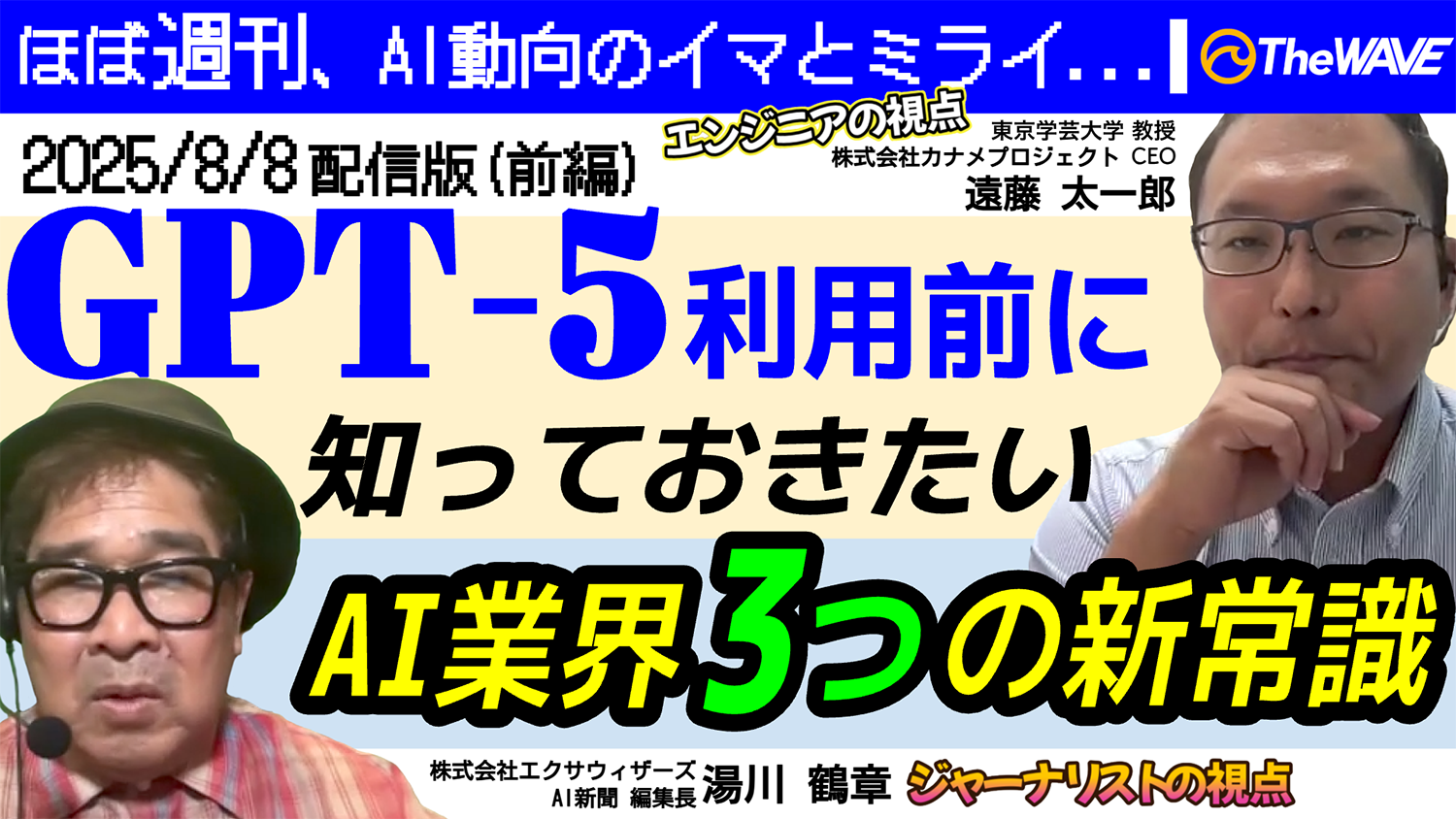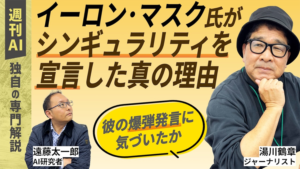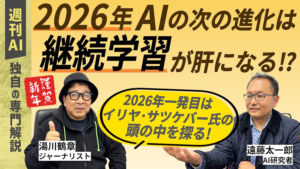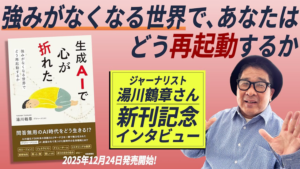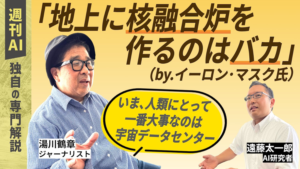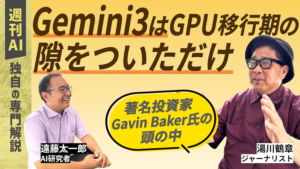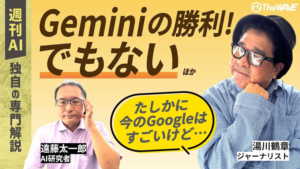本編動画
2025年8月8日に、以下の目次で「ほぼ週刊、AI動向のイマとミライ」動画を配信しました。
0:58 (1)無事に復活したジャーナリストが考える、ほとんどの日本人が知らないAI業界3つの新常識
5:08 (2)「物知りのAI」から「考えるAI」にパラダイムが変わった
10:06 (3)注目すべき進化は「基盤モデル」から「自律型AI」へ
31:01 (4)未来予測は不毛
中編(8/9配信):https://youtu.be/RXT7MCqVILw
後編(8/10配信):https://youtu.be/QTkNVIxUJbQ
各チャプターの概要は以下の通りです。
(1)無事に復活したジャーナリストが考える、ほとんどの日本人が知らないAI業界3つの新常識
(2)「物知りのAI」から「考えるAI」にパラダイムが変わった
・過去の参考動画
https://youtu.be/ZJ9jZPCOsFI
https://youtu.be/jdKxTWUgAL0
https://youtu.be/aPXJLb6-uxM
・目を持ったAI(2012年にDeep Learning。2015年ごろから産業界がAIブームに)→物知りのAI(2017年にtransformer。2023年11月にChatGPT登場で生成AIブームに)→考えるAI(2024年9月にOpenAI o1 論理的思考、リーズニングモデル)
・「考える力は、規模の巨大化からは生まれないという決定的な証拠。2024年に入り全てが変わった。AI研究コミュニティは「テスト時適応」という新しいパラダイムに移行した」(François Chollet氏:考える力を計測するベンチマークARCの開発者)
https://youtu.be/5QcCeSsNRks?si=ZNc–fiR1Rm6Jc96
・「2020年ー21年は、AIモデルが事前学習のNext-token Predictionで大きく成長した。その次のパラダイムは、昨年発表されたOpenAI o1から始まった」(Karina Nguyen氏:OpenAI研究者)
https://www.ai.engineer/summit/2025/schedule/agents-that-cocreate
・「AIは過去のデータのパターンを認識しているだけ」「AIは結局、人間がデータを与えないと賢くならない」といった認識が過去のものになりつつある
(3)注目すべき進化は「基盤モデル」から「自律型AI」へ
・過去の参考動画
https://youtu.be/GxxtjtAALhk
https://youtu.be/3RqfJoa_138
・「最大計算クラスタ=製品優位の神話は2024年に崩壊し、効率化と使い勝手が差別化ポイントに」「2025年の主要モデルは総パラメータ数の拡大をほぼ停止。GPT-5も「単一巨大モデル」ではなく推論時スケーリングで性能を稼ぐ見通し」(Nathan Lambert氏:Allen Institute for AIのLLMのポストトレーニング担当リード/シニアリサーチサイエンティスト、ニュースレター「Interconnects」発行)
・専門メディアの報道
https://www.theinformation.com/articles/inside-openais-rocky-path-gpt-5?rc=qgaeex
・OpenAIの中の人の発言
https://x.com/apples_jimmy/status/1943479993746530450
https://www.bleepingcomputer.com/news/artificial-intelligence/openais-sam-altman-discusses-gpt-5-release-date/ https://x.com/sama/status/1951695003157426645
「今後数か月で、新しいモデル、製品、機能など、たくさんのものをリリースする予定です。多少のトラブルや容量不足が発生する可能性はありますが、どうかご容赦ください」(Sam Altman氏)
・「今までのところはx.aiの圧倒的勝利。 OpenAIは負けを認めざるをえない。GPT-5で大成功を納めなければ、今までの評判を全て失うことになる」(by. Chubby)
https://x.com/kimmonismus/status/1895484639252275216
・GPT-4.5失敗に関する業界事情通の意見
過去の参考動画:https://youtu.be/ZwUTDO9ulK0
・次の大きな進歩はやはり考える力、ただしGPT-5ではない
https://x.com/sama/status/1946569252296929727
https://x.com/polynoamial/status/1946478255831126484
・AI開発においては期待値のコントロールが重要
・今、より重要なのは自律型エージェントの進化 「本当に重要なのはモデルが現実世界で何ができるかということ」(OpenAIのチーフサイエンティストJakub Pachocki氏)
https://www.technologyreview.com/2025/07/31/1120885/the-two-people-shaping-the-future-of-openais-research/
・GPT-5は、人間の介入を最小限に抑えながら複雑なタスクを処理するAIエージェントの性能向上においても、従来のものよりも優れているという
https://www.theinformation.com/articles/inside-openais-rocky-path-gpt-5?rc=qgaeex
・GPT-5はそれほど大きな進化にはならない →今年は基盤モデルの争い、つまり基本的な頭のよさを進化させるという争いではなく、機能、プロダクト、自律型エージェントの争い、つまり目の前のタスクをどれくらいきっちりとこなせるようにできるのか、が競争の焦点
(4)未来予測は不毛
・「次に何が起こるのなんて誰にも分かりません。私たちにも分かりません。賢そうな予測をする人がたくさんいますが、わかっている人は誰もいないと言っていいでしょう」(Sam Altman氏)
・「OpenAIではコンピューターに何ができるかが2、3カ月ごとに突然変わる。コンピューターが、世界で誰も見たことのない新しい能力を突然身につけて、それをベースに製品作りを考えないといけない。コンピューターが次にどんな能力を持つのかは、はっきりと分からない状態、かすかにその兆しが霧の中に見えてきたような状態で、次の製品作りを始めないといけない。これが、私がこれまでに経験してきたテック企業の製品作りと全然違うところだ」(Kevin Weil氏)
・「AIがどんな能力を持つのかに関して我々の予測が当たることもあるが、多くの場合は予測が当たらないからだ。当たらないときはすべてを捨ててピボットするしかない。サイエンスの言う通りに動くしかなくて、サイエンスの言う通りに動くというのが我々の特徴だ」(Sam Altman氏)
https://www.youtube.com/live/-cq3O4t0qQc?si=eKdJ4WiCNvxJKE0K&t=975
・「(国際数学オリンピックで金メダル相当の成績を上げたAIモデルを開発した)Alex Weiは、ほとんどの人が無理だと思っていた方法で成果を上げた。社内の多くの研究者にとっても驚き。(Noam Brown氏) https://x.com/polynoamial/status/1946478255831126484
・「AIの領域で言われるシンギュラリティ(技術的特異点)とは、今までの常識が通用しなくなるフェーズのこと。シンギュラリティ後の未来って恐らく予測不可能だし、今既に予測できない状態になっているということはシンギュラリティの入り口に差し掛かったと言うことなのかな」(湯川)
登壇者情報

遠藤 太一郎
株式会社カナメプロジェクト CEO
国立大学法人東京学芸大学 教育AI研究プログラム 教授
AI歴25年。18歳からAIプログラミングを始め、米国ミネソタ大学大学院在学中に起業し、AIを用いたサービス提供を開始。AIに関する実装、論文調査、システム設計、ビジネスコンサル、教育等幅広く手がけた後、AIスタートアップのエクサウィザーズに参画し、技術専門役員としてAI部門を統括。上場後、独立し、現在は株式会社カナメプロジェクトCEOとして様々なAI/DAO/データ活用/DX関連のプロジェクトを支援する。国際コーチング連盟ACC/DAO総研 Founder等

湯川 鶴章
株式会社エクサウィザーズ AI新聞 編集長
米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。