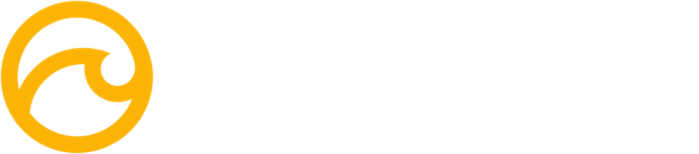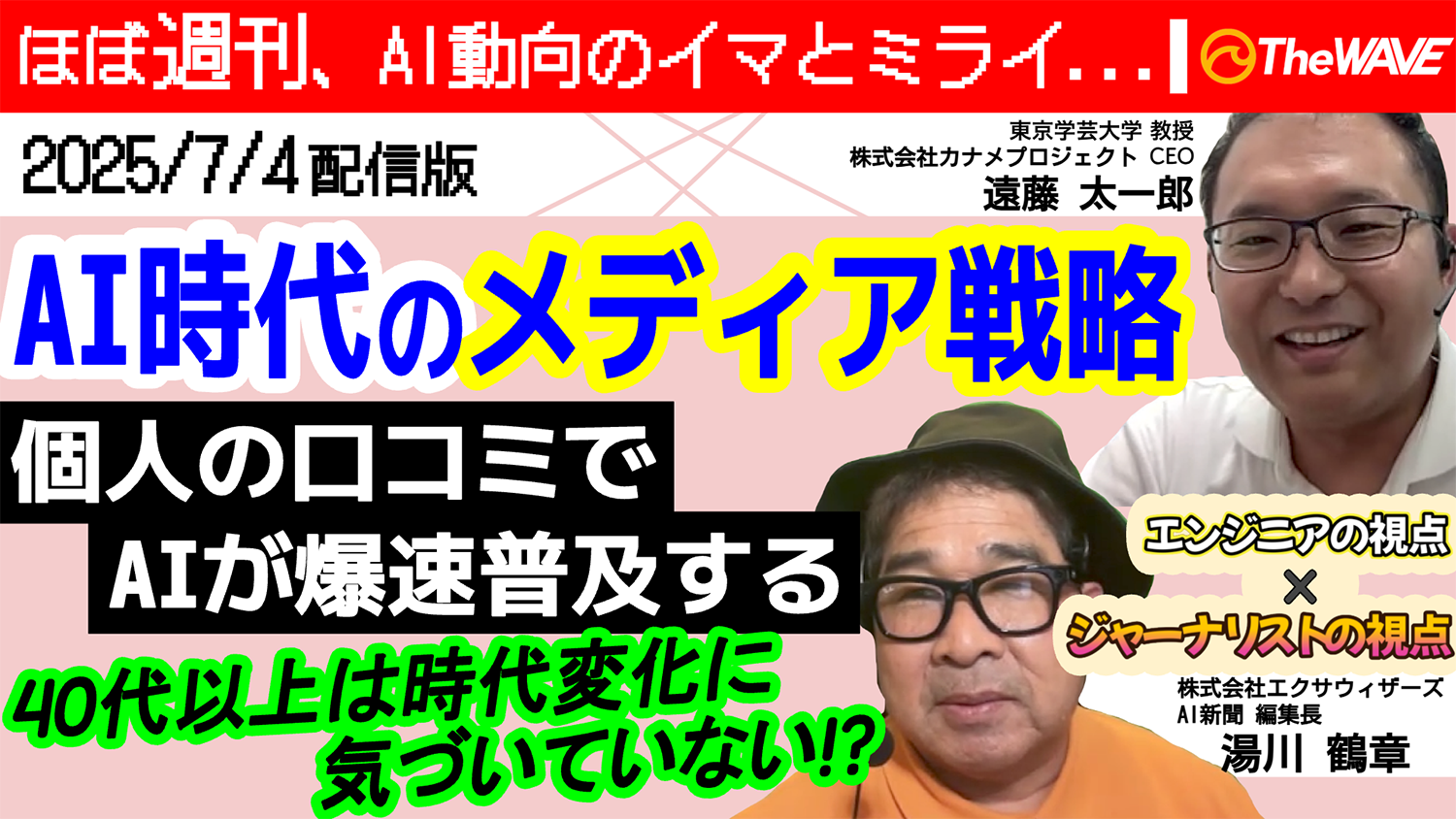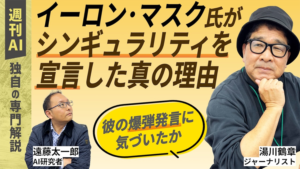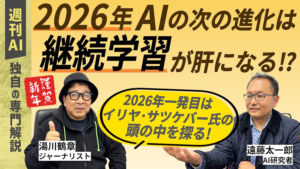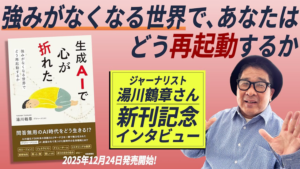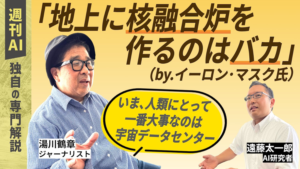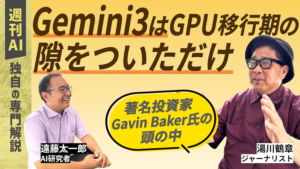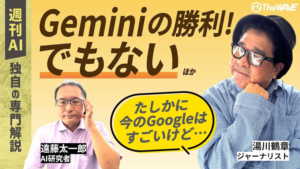本編動画
2025年7月4日に、以下の目次で「ほぼ週刊、AI動向のイマとミライ」動画を配信しました。
0:58 (1)イントロダクション
3:34 (2)AIの個人利用、ここから一気に広がる予感
20:20 (3)CursorやHarvey AI、Lovable、Cal AIなど、モバイル時代とは桁違いの成長率
26:26 (4)40代以上のマーケターは時代変化に気づいていない
41:50 (5)メディアはSNSの尻尾。SNSが向く方向に向く
各チャプターの概要は以下の通りです。
(1)イントロダクション
(2)AIの個人利用、ここから一気に広がる予感
・米シリコンバレーのVC、Mnelo Venturesが6/26に「AI’s Consumer Tipping Point Has Arrived(AIの個人利用がティッピングポイントにきた)」を発表
https://menlovc.com/perspective/2025-the-state-of-consumer-ai/
・ChatGPTリリースから2年半。前例のない規模での習慣形成(アメリカの成人の半数以上(61%)が過去6ヶ月間にAIを利用しており、5人に1人近くが毎日AIを利用)
・Z世代(18~28歳)がAI導入全体をリードする一方で、ミレニアル世代(29~44歳)がパワーユーザー。高齢者も多く使っている
・学生(18歳以上)は85%が利用。仕事をしている人(75%)、していない人52%高所得者の方が利用
・18歳未満の子供を持つ人の79%。子供を持たない人は54%。子供を持つ人で毎日使う人は29%で、持たない人のほぼ倍(主な使用例:育児管理34% 、興味のあるトピックの調査28% 、メモの作成と整理26% AIが相談相手?)
・利用が始まった5つの領域とは
<これからの6つの予測>
・第二の波:専用ツールが主流に
・アシスタントから自動化へ:AIがワークフロー全体を担う
・シングルプレイヤーからマルチプレイヤーへ:複数の人とAI が同じ空間で協調するようになる
・音声AIの飛躍的発展:将来的に統合されるハードウェアデバイスにより、音声はアンビエントAIやプロアクティブAIにとってより自然なインターフェースになる
・物理的なAIが家庭に進出する:人型ロボット、自動運転車
・収益モデルはサブスクリプションを超えて多様化:広告モデル、取引手数料、アフィリエイト収益、マーケットプレイスモデル
(3)CursorやHarvey AI、Lovable、Cal AIなど、モバイル時代とは桁違いの成長率
・アーリーアダプターが個人向け市場を牽引すると同時に所属企業に働きかけB向け市場も牽引。2つの市場からの牽引力により、次世代AI企業はこれまでよりもはるかに速い成長を遂げている
https://a16z.com/ai-enterprise-2025/
・Perplexity AI は無料ユーザ母集団を極めて短期に拡大。Lovable はわずか半年で ARR 6,000 万ドル超 欧州最速クラス。Cursor・Harvey AI などは開発者/専門職コミュニティに一気に浸透、ARR を 4〜5 倍に。Cal AI・Cluely は規模こそ劣るものの、実質ゼロから数千万ドル規模へ 1 年内に到達しており、伸び率では大手に匹敵
・2024年から2025年にかけて、年間経常収益(ARR)が爆発的に増加し、創業数か月~1年で数千万ドル規模に到達する驚異的な成長事例が次々と報告されている
https://sacra.com/c/cursor/
・Lovableはスウェーデン発のスタートアップ。「誰でも英語のプロンプトで本格的なWebアプリを作れる」というAIソフトウェア開発ツール。バイラルマーケティング戦略。18名・消費資金$2MでARR $30M超という効率的成長
https://www.saastr.com/june-30-2025-the-date-where-if-your-team-hasnt-rolled-out-truly-great-ai-into-production-yet-its-time-to-reboot-the-team/
https://www.growthunhinged.com/p/lovable-growth-story
・Cal AI:食事の写真を撮るだけでカロリー計算・記録ができるモバイルアプリ。創業者が高校生。2024年5月サービスローンチ後、口コミとメディア報道でユーザー数が急拡大、8ヶ月で累計500万ダウンロード・月間アクティブユーザー数数百万規模に到達。創業者のZach Yadegari氏(当時18歳)が大学合格より起業を選んだストーリーや、有名大学に15校落ちたエピソードがSNS上で大きな話題となった
https://techcrunch.com/2025/03/16/photo-calorie-app-cal-ai-downloaded-over-a-million-times-was-built-by-two-teenagers/
(4)40代以上のマーケターは時代変化に気づいていない
・Cluely:大学を退学になった21歳Roy Lee氏が開発した「何にでもズルできるAI」。500万ドルの資金調達に成功
https://www.youtube.com/watch?v=U48dckKCK4g&t=955s
・一種の炎上商法。Roy Lee氏に起こった様々な出来事をTwitterで積極的に発信していったことで、話題になり、シリコンバレーの投資家たちのオファーが殺到。結果的に500万ドルの資金調達に成功する
・「今はズルと見られてるけど、2年後にはこれが普通になる」
https://youtu.be/yap8iSeY8vE?si=Y76ELWnIWep6i_QD
※映画「ソーシャル・ネットワーク」の音楽を流用し、シーンを真似る形で制作
・X(旧twitter)のアルゴリズムの癖と対処法。意図的に物議を醸すシナリオを作り出すことで、アルゴリズムの恩恵を受けようとしている。「50%の人が非常に強いネガティブな反応を示す」ような動画こそが、主流でバイラルになる
・Cluelyの口コミマーケティングの思想:ディストリビューション第一主義の会社。月に10億ビューを獲得できれば、販売するものが何であれ、人々は買う。注目を得れば金持ちになれる。単なるブランド認知ではなく、「マインドシェア」の獲得を重視。マインドシェアとは人々の間で話題になり、強い感情的な反応を引き起こすこと
・「若くなければ、今の時代を感じることができない。大企業のマーケティング担当者は40歳以上なので、これが今の方法だと気づかない。X上でわれわれのやり方が気に入らない人は、インスタグラムのコメント欄を見れば時代が変わったことに気づくだろう」
・Lee氏自身がClueyの顔となり、自身のパーソナルブランドと会社のブランドを一体化。「トップAI企業が高性能な基盤モデルを出し続ける中で、基盤モデルの最も優れたディストリビューターとなることを目指す。必要なのは技術力よりも、ブランド力やマインドシェア」
(5)メディアはSNSの尻尾。SNSが向く方向に向く
https://www.youtube.com/watch?v=dfGANTiLlwE&t=973s
・シリコンバレーの老舗VCの中では後発組であるAndreessen Horowitze、略称「a16z」主催のイベント「a16z LP Summit 2025」の中で、後発でありながらシリコンバレーVCのトップティアに上り詰めることができた理由として①組織形態、②メディア戦略を挙げている
・ミームとは、画像やキャッチフレーズなど、1文や1つの画像で拡散できるアイデアや物語のこと
・例:a16z が2011年に発表したエッセイのタイトル「Software is eating the world」は、ミームとして広く拡散され、このフレーズが14年経った今でもニュースメディアや政府の白書などでそのまま引用されている
・ミームは ①短くて使いやすい → ②そのまま広くシェアされる → ③誰にでも理解できる概念になる、という形で社会に影響を与えることになる
・ソーシャルの向く方向と反対の方向に進むエネルギーと時間がレガシーメディアにはない。追随するか、無視するかだけ。「犬」の向く方向に「尾」も動く
・「旧メディアが尾」の理由:①経済的インセンティブ、②編集コストの削減、③リアルタイム検証が困難
・SNSの話題は、2〜3日の短いサイクルで発生し、その後に急速に沈静化する 「この絶え間ないパニックサイクルは、人々を精神的に疲弊させる。なのでこれに疲れた人たちが本質を求めて、Lex Feidman氏のポッドキャストのような三時間から六時間の長尺コンテンツに流れる」 (Marc Andreessen氏)
・ミームを制するOODA(ウーダ)ループ:米空軍の戦闘理論家ジョン・ボイドが提唱した、Observe(観測)-Orient(状況判断)-Decide(意思決定)-Act(行動)のループ
・「Launch fast, meme faster(製品を速く出せ、ミームはもっと速く出せ)」Marc Andreessen氏
・a16zのメディア戦略から見るミームの具体策(フォーマットの最適化、自社メディアと配信網の維持、有望ミームを見極めて即対応、ミーム製造サイクルを内製化、規制・政策向けの“正史”版を同時発行)
個別テーマ解説動画
また、各テーマに分割した動画も配信しました。興味のあるトピックに応じてご覧ください。
【切抜解説】「40代以上のマーケターは時代変化に気づいていない」と豪語するCluely CEOの思想
0:00 「何にでもズルできるAI」を標榜
3:01 大学を退学になった21歳・Roy Lee氏のこれまで
6:24 X(旧Twitter)のアルゴリズムの癖と対処法
8:19 InstagramとLinkedIn対策
9:34 Cluelyの口コミマーケティングの思想「ディストリビューション第一主義」
12:41 Lee氏自身がCluelyの顔に
13:25 必要なのは技術力よりも、ブランド力やマインドシェア
【切抜解説】これからの時代、「ミーム」を制する者がメディアを制す!
0:00 a16zが後発でも成功した2つの理由
1:08 ミームを制する者がメディアを制す
2:39 SNSが犬で、オールドメディアが尾っぽ
8:16 人々が3時間〜6時間の長尺コンテンツに流れる理由
9:22 「製品を速く出せ、ミームはもっと速く出せ」
10:44 a16zが実践してきたミーム具体策
※サムネイル画像はNguyen DungによるPixabay画像を活用
【切抜解説】創業1年以内で数十億円規模に到達!?脅威的に成長するAIサービスの牽引役は「個人ユーザー」だ
0:00 AIの「個人利用」がティッピングポイントにきた
2:00 Z世代がリードするも、ミレニアル世代がパワーユーザー
4:13 18歳未満の子供を持つ人の79%がAIを利用している!?
5:53 アメリカでAIの個人利用が進む5つの領域
13:56 これから起こること、6つの予測
16:44 モバイル時代とは桁違いの成長率を誇るAIベンチャーたち
19:54 スウェーデン発「Lovable」:ローンチ後6カ月で年間経常収益約84億円に到達
21:13 高校生創業「Cal AI」:ローンチ1年弱で年間経常収益約49億円規模に成長
登壇者情報

遠藤 太一郎
株式会社カナメプロジェクト CEO
国立大学法人東京学芸大学 教育AI研究プログラム 教授
AI歴25年。18歳からAIプログラミングを始め、米国ミネソタ大学大学院在学中に起業し、AIを用いたサービス提供を開始。AIに関する実装、論文調査、システム設計、ビジネスコンサル、教育等幅広く手がけた後、AIスタートアップのエクサウィザーズに参画し、技術専門役員としてAI部門を統括。上場後、独立し、現在は株式会社カナメプロジェクトCEOとして様々なAI/DAO/データ活用/DX関連のプロジェクトを支援する。国際コーチング連盟ACC/DAO総研 Founder等

湯川 鶴章
株式会社エクサウィザーズ AI新聞 編集長
米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。